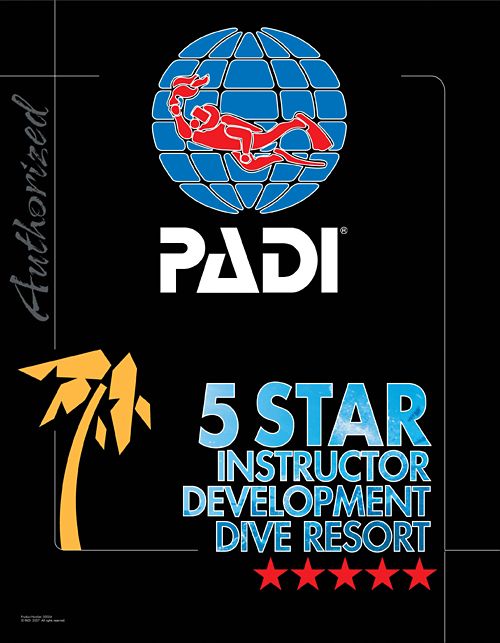
【インストラクターが本音で解説】ダイビングライセンスの指導団体は「PADI」を選ぶべき、5つの理由。
こんにちは!
三浦半島でダイビングスクール「三浦 海の学校」を運営している、インストラクターの吉田です。
「よし、ダイビングを始めてみよう!」 そう決意したあなたが、まず最初にインターネットで検索するのは、きっと「ダイビング ライセンス 取得」 といった言葉かもしれませんね。
すると、たくさんのダイビングショップの情報が出てきて、「どこでライセンスを取ればいいんだろう…」 と、最初の壁にぶつかるかもしれません。 お店の雰囲気、料金、通いやすさ…選ぶ基準はいろいろあって、本当に迷いますよね。
でも、ちょっと待ってください。
実は、その「お店(ショップ)選び」と同じくらい、いや、もしかしたらあなたの今後のダイビングライフを考えると、それ以上に大切かもしれない、もう一つの「選び方」 があることをご存知でしょうか?
それが、**「指導団体」 **を選ぶ、ということです。
「しどうだんたい…? なんだか難しそうな話だな…」 そう思ったかもしれませんね。 大丈夫です。今日は、このちょっぴり分かりにくい「指導団体」について、そして、その中でもなぜ、ぼくが**「PADI(パディ)」**という指導団体を圧倒的におすすめするのか、その理由を、インストラクターとしての本音と、これからダイバーになるあなたの目線、その両方から、じっくり、たっぷりお話ししたいと思います。
この記事を読み終える頃には、きっとあなたのライセンス選びの視点がガラッと変わり、もっと自信を持って、最高の一歩を踏み出せるようになっているはずですよ。
そもそも「指導団体」 って、いったい何?
まず、基本のキからお話ししましょう。 ぼくらがダイビングをする時に必要になるライセンスカード、通称「Cカード」。これは、車の運転免許証のように国が発行しているものではなくて、民間の団体が発行している「技能認定証」 なんです。
そして、そのCカードを発行している大元締めが**「指導団体」 **です。
ざっくり言うと、指導団体とは、 「どうすれば、みんなが安全に、楽しくダイビングができるかな?」 ということを、長年の経験や科学的なデータに基づいて研究し、世界中の誰もが同じように学べる「教育カリキュラム」 や「教材(テキストやDVDなど)」を作っている、いわば**『ダイビング教育の総本山』**みたいな組織です。
そして、ぼくたちインストラクターは、この指導団体が決めたカリキュラムと基準に沿って、皆さんにダイビングの知識とスキルを教えるための、厳しいトレーニングを受けています。
世界には、本当にたくさんの指導団体があります。 日本でよく名前を聞くのは、ぼくが所属しているPADIの他に、NAUI(ナウイ)、SSI(エスエスアイ)、**CMAS(クマス)**などでしょうか。それぞれに長い歴史や、少しずつ違う哲学、特徴があります。
「え、じゃあ、どこで取っても同じじゃないの?」 そう思うかもしれませんが、実は、どの指導団体のCカードを持つかによって、あなたのダイビングライフの「快適さ」 や「安心感」、「将来の選択肢の広さ」が、結構変わってくる可能性があるんです。
なぜ「PADI」 が圧倒的におすすめなの?【お客様側の3つのメリット】
では、ここからが本題です。 数ある指導団体の中で、なぜぼくは「PADI」 を強くおすすめするのか。 まずは、これからライセンスを取得するあなたの立場、つまり「お客様側」に立って、その具体的なメリットを3つ、ご紹介します。
メリット1:世界No.1のシェアがもたらす「絶大な安心感」 と「利便性」
これが、PADIを選ぶべき最大の理由と言っても過言ではないかもしれません。 PADIは、世界180以上の国と地域で活動する、正真正銘、世界最大のダイビング指導団体です。
どれくらい最大かというと、全世界で発行されるCカードの、なんと約6割がPADIのカードだと言われています。 ざっくり言うと、世界中のダイバーの半分以上が、あなたと同じ「PADIファミリー」 の仲間、ということになるんです。
「シェアがNo.1なのが、そんなに大事なの?」 ええ、すごく大事なんです。この「世界標準」であるという事実が、あなたに2つの大きな恩恵をもたらしてくれます。
一つは、「どこに行っても通用する」 という圧倒的な利便性。 例えば、あなたが将来、「ハワイで潜ってみたい!」「沖縄の離島の海が見たい!」と思って、現地のダイビングショップに申し込んだとします。 その時、PADIのCカードを持っていれば、世界中のほぼ100%のショップで、何の問題もなくスムーズに受け入れてもらえます。お店の人も「ああ、PADIのダイバーさんね。 OK!」と、すぐにあなたのスキルレベルを理解してくれるでしょう。
でも、もし、あまり知られていないマイナーな指導団体のCカードだったら…? もしかしたら、「ん?これは何のカードだろう?」「どんなトレーニングを受けたのかな?」と、お店の人に確認されたり、場合によっては、スキルチェックのために体験ダイビングからの参加をお願いされたり…なんて可能性も、ゼロとは言い切れません。 せっかくの旅行先で、そんな風に余計な時間や手間がかかってしまったら、ちょっと残念ですよね。
二つ目は、「世界共通の基準」 という安心感。 PADIの講習は、世界中どこで受けても、教える内容や安全基準が統一されています。
つまり、あなたが日本で受けたPADIの講習と、オーストラリアで誰かが受けたPADIの講習は、基本的には全く同じクオリティが保証されている、ということです。 この「世界標準の安全性」が担保されているというのは、これから海という未知の世界に挑戦するあなたにとって、何物にも代えがたい安心材料になるはずです。
メリット2:初心者でも分かりやすい!「高品質な教材」 と「学習システム」
ダイビングのライセンス講習では、海に潜る実習だけでなく、安全に潜るための大事な知識を学ぶ「学科講習」 があります。
PADIが優れているのは、この学科講習のシステムが、非常に現代的で、学習しやすいように工夫されている点です。
特に**「eラーニング」 **のシステムは秀逸です。 これは、スマホやパソコンを使って、オンラインで好きな時間に、自分のペースで学科の勉強を進められるというもの。 「仕事が忙しくて、まとまった時間が取れない…」という方でも、通勤中の電車の中や、寝る前のちょっとした時間を使って、無理なく学習を進めることができます。
そして、その教材の内容も、写真や動画がたくさん使われていて、視覚的にすごく分かりやすいんです。 難しい専門用語も、アニメーションなどで丁寧に解説してくれるので、「勉強はちょっと苦手で…」という方でも、きっと楽しみながら知識を身につけることができると思います。
「せっかく始めるなら、ちゃんと理解して、しっかり身につけたい」
そんなあなたの真面目な気持ちに、PADIの高品質な教材は、きっと応えてくれますよ。
メリット3:飽きさせない!「ステップアップの道筋」が明確で多彩
ダイビングは、ライセンスを取ったら終わり、ではありません。 そこからが、本当の冒険の始まりです! PADIの素晴らしいところは、その冒険の道筋、つまり**「ステップアップ」のコース**が、非常に分かりやすく、そして魅力的に用意されていることです。
最初のライセンス「オープン・ウォーター・ダイバー(OWD)」を取得したら、 ↓ 次は、遊びの幅を広げる**「アドヴァンスド・オープン・ウォーター・ダイバー(AOW)」。ディープダイビング(少し深い場所への潜り方)や、ナビゲーション(水中での方向感覚)などを学びます。 ↓ さらに、バディを助ける知識とスキルを身につける「レスキュー・ダイバー」。 ↓ そして、アマチュア最高峰のランクである「マスター・スクーバ・ダイバー」 **へ。
こんな風に、明確なステップアップの道が示されているので、「次の目標」が見つけやすく、モチベーションを維持しながら、ダイバーとして成長していくことができるんです。
それだけではありません。 PADIには、特定の分野をとことん追求できる**「スペシャルティ・コース」 **が、驚くほどたくさんあります。
「水中写真がうまくなりたい!」 「沈没船を探検してみたい!」 「魚の名前にもっと詳しくなりたい!」 「夜の海、ナイトダイビングに挑戦したい!」
そんな、あなたの「もっと!」という好奇心に応えてくれるコースが、必ず見つかるはずです。 この選択肢の多さも、世界No.1の指導団体ならでは。PADIなら、あなたがダイビングに飽きてしまうことは、きっとないでしょう。
ぼくが「PADI」を選ぶ理由【インストラクター側の2つのメリット】
さて、ここまでお客様側のメリットをお話ししましたが、今度は、教える側のプロである、ぼくたちインストラクターの視点から、なぜ「PADI」が信頼できるのか、その理由をお話しさせてください。 これは、普段あまり聞けない話かもしれませんが、皆さんの安全に直結する、とても大事なことなんです。
メリット4:インストラクターに課せられる「厳格な安全基準」 と「質の高いトレーニング」
ぼくたちPADIのインストラクターは、お客様に自信を持って「安全ですよ」 と言うことができます。 なぜなら、PADIが定めている**「安全基準」**が、世界中の事故事例や科学的データを元に、非常に厳格かつ実践的に作られているからです。
講習で教えるスキルの手順、引率できるお客様の人数、潜れる水深など、あらゆることに細かいルールが定められています。 ぼくたちは、このルールを絶対に守ることを誓って、活動しています。 「この基準さえ守っていれば、事故のリスクを最大限に減らすことができる」 そう心から信じられる世界標準のルールがあるからこそ、ぼくたちは、自信と責任を持って、皆さんを海へお連れすることができるんです。
そして、PADIのインストラクターになるためのトレーニングは、正直言って、かなり大変です(笑)。 知識、スキル、指導力はもちろん、安全管理能力やプロとしての意識まで、本当に厳しい基準で評価されます。
さらに、大事なのは、インストラクターになった後も、毎年必ず資格を更新しなければならない、という点です。 その際には、最新の指導基準や安全情報を学び、テストを受けることが義務付けられています。
つまり、ぼくたちPADIのプロは、「一度資格を取ったらおしまい」ではなく、常に自分自身の知識とスキルをアップデートし続ける義務があるんです。
この「質の維持」に対する厳しい姿勢こそが、PADIが世界中で信頼されている、何よりの証拠だとぼくは思っています。
メrito5:世界的なネットワークと「継続的な教育」への意識
PADIは、世界最大の指導団体であると同時に、世界最大の「プロダイバーのコミュニティ」 でもあります。 世界中のインストラクターやショップと繋がっていて、常に新しい情報や指導法が共有されています。
このグローバルなネットワークがあるおかげで、ぼくたちも常に世界の最新動向を学び、自分の指導に活かすことができます。
また、PADIは「ダイビングは生涯学習である」 という考え方を非常に大切にしています。 先ほどお話しした多彩なステップアップコースも、まさにその考え方の表れです。 ダイバーが常に新しい目標を持ち、学び続けることで、スキルが向上し、安全意識も高まり、結果として、もっと豊かで安全なダイビングライフを送ることができる。
そんな「継続教育」のサイクルを、指導団体としてしっかりとサポートしてくれる。 この姿勢も、ぼくがPADIを信頼し、皆さんにおすすめする大きな理由の一つです。
でも、一番大事なのは…「指導団体」 と「ショップ選び」の最終結論
ここまで、PADIの素晴らしさを熱く語ってきてしまいましたが、最後に、一番大事なことをお伝えします。
「じゃあ、PADIの看板を掲げているショップなら、どこでも良いの?」 答えは、「いいえ」です。
もちろん、PADI以外の指導団体がダメだ、なんて言うつもりも全くありません。どの団体にも、素晴らしいインストラクターはたくさんいます。
最終的に、あなたのダイビングライフが最高のものになるかどうかを決めるのは、 「信頼できる指導団体(ぼくはPADIを強く推奨しますが!)の基準を満たした上で、さらに『あなたに合った、心から信頼できるショップとインストラクター』を見つけること」 これに尽きます。
どんなに優れたカリキュラムや教材があっても、それを伝えるインストラクターとの相性が悪かったり、教え方が雑だったり、あるいは、お店の雰囲気が自分に合わなかったりしたら、せっかくのダイビングも楽しくなくなってしまいますよね。
ですから、指導団体として「PADI」を一つの大きな安心材料とした上で、最終的には、
- あなたのペースに合わせて、少人数でじっくり教えてくれるか?
- あなたの質問や不安に、親身になって答えてくれるか?
- 安全管理に対する意識が高く、器材のメンテナンスもしっかりしているか?
- そして何より、「この人から習いたい!」「このお店で続けたい!」 と、あなたが心から思えるか?
といった視点で、ぜひ、いくつかのショップを比較検討してみてください。
まとめ:最高のダイビングライフは、最初の「選択」から始まる
長いお話に、最後までお付き合いいただき、本当にありがとうございました。
ダイビングライセンスの「指導団体」を選ぶということは、これからあなたが建てていく「ダイビング」 という名の家の、**「基礎」**を選ぶようなものかもしれません。 その基礎が、世界標準で、堅固で、信頼できるものであれば、その上に、あなたは安心して、自由で、創造的な家(=ダイビングライフ)を建てていくことができます。
PADIは、その「基礎」として、ぼくが自信を持っておすすめできる、最も信頼性の高い選択肢です。
あなたのダイビングライフが、安全で、楽しくて、一生モノの、かけがえのない宝物になるように。 その最初の大切な一歩で、もし何か迷うことや、分からないことがあれば、いつでも気軽に、ぼくに相談してくださいね。
海の世界への扉を開ける、あなたの最高のスタートを、心から応援しています!
◆ 三浦 海の学校のご紹介 都心から日帰りOK! PADIの基準に基づいた、丁寧で安全なダイビング講習ならお任せください。 あなたの「やってみたい!」を、経験豊富なインストラクターが全力でサポートします。 詳しくはウェブサイトをご覧ください。
タグ